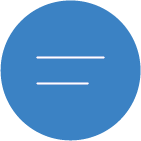1. はじめに
スマホやPCで手軽に曲作りができる「作曲アプリ」。
GarageBandやBandLabなど、無料・有料問わず誰でも音楽制作を楽しめる時代になりました。
しかし、「作曲アプリで作った曲の著作権は誰のもの?」という疑問を持つ人も増えています。
結論から言うと、多くの場合は作曲した本人に著作権が発生します。
ただし、アプリの利用規約や使用した素材によっては例外があり、場合によっては商用利用ができないケースもあります。
この記事では、作曲アプリと著作権の関係をわかりやすく解説し、トラブルを避けるための注意点や、自分の曲を守る方法もご紹介します。

2. 作曲アプリとは?
2-1. 定義と特徴
作曲アプリとは、スマホやPCで楽曲制作を可能にするソフトウェアのことです。
機能はアプリによって異なりますが、主に以下のような機能を持ちます。
- MIDI入力によるメロディ作成
- 音源ライブラリ(ピアノ・ギター・ドラムなど)
- 録音・編集・ミキシング
- エフェクト追加(リバーブ、EQ、コンプレッサーなど)
2-2. 代表的な作曲アプリ例
| アプリ名 | 特徴 | 商用利用可否 |
|---|---|---|
| GarageBand | Apple公式、初心者でも直感的操作が可能 | 可(Apple素材もOK) |
| BandLab | 無料・クラウド保存・SNS連携 | 可(ループ音源もOK) |
| FL Studio Mobile | EDM制作に強い | 可(サンプル規約要確認) |
| Logic Pro / Cubase | プロ仕様の高機能DAW | 可(プラグイン規約要確認) |
3. 著作権の基本知識
3-1. 著作権とは?
著作権(Copyright)とは、創作した作品を保護する法律上の権利です。
音楽の場合、メロディーや歌詞、編曲などが対象になります。
ポイントは、創作した瞬間に自動的に発生すること。
登録手続きや申請は不要で、オリジナルであれば権利が守られます。
3-2. 著作者と著作権者の違い
- 著作者:実際に曲を作った人
- 著作権者:著作権を保有する人(契約によっては会社や他者になる場合あり)
4. 作曲アプリで作った曲の著作権は誰に?
4-1. 基本ルール
ほとんどの場合、曲を作った本人に著作権が発生します。
4-2. 例外的なケース
- アプリの利用規約で権利譲渡を求められている場合
- 他人が作った音源(ループやサンプル)をそのまま使用した場合
- 著作権保護対象の曲を改変・引用した場合
5. サンプル音源やループ素材の注意点
作曲アプリには多くの場合、サンプル音源やループ素材が付属しています。
これらは便利ですが、著作権上の扱いに注意が必要です。
- 著作権フリー:自由に使用可能(GarageBandのループ音源など)
- 商用利用制限あり:営利目的では不可
- クレジット表記必須:利用する際に制作者名を明記する必要あり
6. 著作権侵害を防ぐためのポイント
- 他人の曲やメロディをコピーしない
- 歌詞も独自のものを作成する
- アプリの利用規約を必ず読む
- 商用利用の場合は特に注意
- 素材の権利情報を確認する
7. 自分の曲を守る方法は?
- 制作日やファイルを保存し、タイムスタンプを残す
- 郵送で自分宛に送る「Poor Man’s Copyright」
- 著作権登録サービス(JASRAC、NexToneなど)
- ブロックチェーンによる権利証明
8. よくある質問(Q&A)
Q1. 作曲アプリのサンプル音をそのまま使っていい?
→ 利用規約を確認し、商用利用可かどうかを必ずチェック。
Q2. 著作権フリーとロイヤリティフリーの違いは?
→ 著作権フリーは権利放棄、ロイヤリティフリーは利用料不要だが権利は残る。
Q3. YouTubeで公開して収益化できる?
→ 可能だが、使用素材の商用利用可否を確認すること。
9. まとめ
作曲アプリは便利ですが、著作権を理解して正しく使うことが必須です。
ルールを守れば安心して音楽活動を続けられ、万が一のトラブルも避けられます。
➡️詳細・お申し込みは お問い合わせフォーム へ